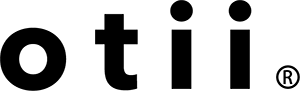息子を連れて、安全な登山道から、少しだけ離れて。
20 August 2021

子どもの頃、大キライだった登山。大人になって知った楽しさを、息子にも享受してもらいたい。行き着いたのは、日常と非日常がせめぎ合う、冒険道。
CONCEPT
『小さな旅の記録~your solo trip~』<インタビュー連載>
"旅"をコンセプトに開発された「solo trip collection秋冬」のアイテム達を
記念して、新たなプロジェクトが始動。
otii®︎の理念に共感してくれた沢山のゲストに、
"旅"をテーマにお話を伺いました。
馴れ親しんだ日常から、ほんの少しだけ離れてみる。
たったそれだけで、そこには「小さな冒険」が溢れていました。
 |
ヤマガスキナダケさん |
息子を連れて、安全な登山道から、少しだけ離れて。
ーーーー家族3人での登山を魅力的なイラストとともに発信しているヤマガスキナダケさん。お子様はおそらくゲームが手放せない年頃だと思いますが、どうやって山に誘い出したのでしょうか。
まず僕と奥さんの2人で登山を始めたのが、家族登山のきっかけでした。僕が会社の同僚から登山に誘われ、練習がてら近所の山に登るのを奥さんに付き合ってもらい、何度か2人で登り「登山、めちゃくちゃおもしろいな!」と。
息子への誘い文句はいろいろ言ったと思いますが、とにかく大人が想像し得る「子どもが嫌だろうなと思う要素」を極力減らして。当時6歳の彼は、意外にもすんなりと来てくれました。

ーーーー子どもにとって体力的にハードだったのではないでしょうか?
そうですよね。実は僕自身、登山に対してトラウマがあったんですよ。3,4歳頃、生粋の山男だった祖父に過酷な登山に連れられた、辛い記憶しかなかったんです。
祖父は戦争で怪我をして帰ってきてからは仕事に就かず、保証を受けて生きていた人でした。それで趣味というか、年間の半分以上は山で生活していて、祖父の家に行くと山から持ってきた木を使って何かを作っているか、山に入っているか、どちらかで。
そんな祖父に、よく愛宕山に連れていかれまして。初日の出登山をよく覚えています。1月の極寒のなか、登山道なんて通らず、道なき道を祖父がナタで雑草を切り倒しながら登り、山頂を目指すんです。
いま振り返ると、大人にとっては楽しさしかないですが、子どもからするとつらさしかないですよ。
ほかにも、中学時代、愛宕山で生徒を競わせるイベントがあったんです。それが子どもながらにイヤでイヤで。1学年全員で、ヨーイドンで麓から山頂に向けて一斉に走るんです。奥さんも同じ地域の学校で同じイベントがあり、10位以内に入っていたそうですが、厳しい部活に入っていて上位到着がしなければならないプレッシャーがあり、やっぱりトラウマになったようで。夫婦揃って、見事に登山に対してネガティブなイメージしかありませんでした。でも、大人になってから登山をして「こんなに楽しいものだったのか!」と、ネガティブさが一掃されました。
そんな経験から、子どもにはしんどい登山をさせたくなかったので、低山だったり、休憩をこまめにとったり、山頂を目指さないし、目指すにしても山頂付近までロープウェイで行ける山を選んだり、そういう工夫をしてきました。

ーーーー「山頂を目指さない」とすると、登山の楽しみ方や目的はどんなことでしょうか。
さきほどおっしゃっていましたが、やっぱりゲームに寄っていく世代ですよね。かといって熱中症への注意喚起が盛んな昨今で、昔よりも外遊びについて消極的な時代の流れもあります。そんな時流について「このまま育ったら、自然に対して苦手意識を持ったままになってしまうのでは」と思い、自然のなかに放り出されることで、自然のもので工夫して遊べるようになってほしいというのが願いのひとつでもありました。
それで当初は、息子と登る予定の山に事前に奥さんと登り、「ここのポイントは遊べそうだな」なんて想像して、いざ息子を連れて「ここでこんなことをしたら楽しいよ」と案内すると、基本的に子どもが親の思い通りにいくことはないんです。子どもには子どもの目線があり、意外なことで遊び始めたりするんですよね。

ーーーーたとえば、お子様はどんなことに興味を持ちましたか?
ずっと蟻の行列を見ていて、これは衝撃でした。普段の彼を見ていたら、ゲームに慣れているからいろいろなことがせっかちになりがちなんです。でもずーっと蟻だけを見ていて、こんなにのんびりとした時間の使い方ができるのか、と、びっくりしました。それに、普段は触れることのない虫なんかも平気で触れたりして、意外なことばかりでした。
とはいえ、大人がサポートしないと登山の楽しみ方はわからない年頃であることには変わりなく。子どもが思う自然への苦手意識を人一倍知っていた僕らだからこそ、うまくサポートできていたのかなと思います。

ーーーー子どもとの登山は、特に想定外に備える必要がありそうですが
そうですね、登山歴が浅かった頃に想定外に遭遇したことがあります。僕らがいま低山中心に登っているきっかけのひとつでもあるんですが、家族3人でアルプス登山に挑んだときのことです。
僕も奥さんも初めてのアルプスで、万全すぎるほどの準備をしたつもりでしたが、悪天候に見舞われて強行突破してしまったんです。いま思うと登山を中止にしなければならないほど危険な環境でした。登るうちに嵐のようになり、テント場に着いたら1つしか張られていない、ほぼ誰もいない状況で。僕は「ラッキー!空いてる」くらいに思っていましたが、みんな中止にしていたってことなんですよ。
いざテントを張り中にいると、一晩中、激しい雨音とテントが飛ばされるのではという強風が一晩中続きました。

ーーーーお子様は怖がっていましたか?
いや、子どもは怖いもの知らずなもので、楽しそうにしていました。僕ら大人こそ恐怖心だらけ。いままで読んできた遭難エピソードが頭をよぎり、もっとも恐ろしいことは体が濡れて体温が下がることだと知っていますから、奥さんは眠れずに一晩中起きていたようです。翌朝は、さすがに山頂を目指さずに下山しました。
ーーーーそれがきっかけで、家族登山は、「むりをしない低山」が条件のひとつになったのですね。
同じように、登山中に日没が来たことがきかっけで、いざ想定外に遭遇すると、ほんとうに大変なんだなと実感したこともあります。山って、夜になると一変するんですよ。初めてエマージェンシーキットを開けてライトを使いましたが、ライトを消したら真っ暗闇で、点けても足元しか見えず、目的地が見えないので不安で気が気ではなくなります。
そこは初見の山で、子どもを危険に晒す状態にしてしまったことへの反省と、暗闇を歩くことについてどこか冒険心をくすぐられる自分もいたんですよ。
ならばと、「歩き慣れた山ならおもしろさをひしと感じられるのでは」と、近所の山で「日没後の登山練習」と称して、暗くなってから下山するナイトハイクをやることにしたんです。
知っている山ならば「ここを下るだけ」と道もわかりますから、イベントとして楽しむことができるんです。
ーーーー夜行性の動物などに遭遇しそうですね。
めっちゃ気配を感じます。日中は、ガサッと音がしてそちらを見て何もいなかったら「気のせいか」で済みますが、夜に同じことが起きると気のせいで終わらないんですよ。「なんかいる。ずっとなんかいる!」となるんです。視覚で「いない」ということが確認できなから。
日中とは違う景色や空気感による、ドキドキ感は、夜の登山じゃないと味わえないですよね。子どもも楽しんでいました。
ーーーーヤマガスキナダケ家の、登山のハイライトはどんな瞬間でしょうか。
うーん、うちは全員グルメじゃないから“食”ではないですし、景色には普通に感動しますが……正直、普段リビングでもたらされる楽しさや感動と、そんなに変わらないんですよね。日常の遊びの延長、自分の家の裏庭という感覚で、なんなら電波の届く場所にいたら奥さんと無言でそれぞれ動画を観たりしていますから。そのくらいのほうがいいんじゃないのかなと思っています。
以前は、1人で登るときは何かと戦っているのかというくらい、夏場に汗だくで高山に登るようなスタンスでした。それも楽しい一方で、僕らはそれがむりだろって話で。なんだかんだ“趣味”ですし、そこに競技性を求めるよりも、いかに自然の中に入って癒やされるか刺激を受けるかではないか、と。登山歴6年目のいまは、いかにむりせずに楽しむかというところに落ち着きました。特に子どもは、疲れたら成立しませんから。登山って、絶対に根性論じゃないと思うんです。何かを「目指そう」となると、時間の制約もあるし、必ずしんどくなってしまう。だから、目的を持たず、山頂まで行かずとも途中でやめていいんですよ。
一番大事なのは、親が楽しんでいる姿を見せることなんですよね。あれだけいやだった祖父との登山も、祖父が楽しんでいる姿を見ていたからこそ、僕はこうやって大人になって同じことをしているのかもしれません。

ーーーー山頂を目指さない登山を“旅”とするならば、ヤマガスキナダケさんにとって、旅とは?
僕らの登山は、大きなハプニングは求めたくないけど、淡々としたなにもない日常はすごしたくない、という、矛盾する2つのせめぎあいの線上での旅ーーという感じがしますね。
非日常と日常の境目を歩くバランスって、すごく大事だと思うんです。登山道に例えると、逸れすぎると危険だらけだけど、人間が作った安全なだけの道はスリリングが皆無ですよね。僕はその境目、日常のスパイスになり得るちょっとした刺激を、うまいこと見つけて歩いている気がします。たとえば僕は息子に地図読みを教えているんですが、GPSに頼らずに紙の地図とコンパスで目的地を目指す楽しみ方です。息子とは慣れた山でしかやりませんが、地図から浮かび上がった、登山道から離れたルートを歩いてみたりします。冒険心がくすぐられる一方で、安心感あっての冒険であることが大事です。
そういったバランス感覚を、自然に近づくことで子どもに養ってもらえたら、世の中を生きることが楽しくなるのではと思います。
[ GUEST ]
NAME : ヤマガスキナダケ
INSTAGRAM : @yamagasukinadake
AREA : kyoto
[ INTERVIEWER / WRITER ]
NAME:有山千春
AREA : TOKYO
JOB : FREELANCE WRITER
PROFILE:制作会社、出版社を経て2011年よりフリー。主に週刊誌、月刊誌、書籍構成。行くなら最果てと、猥雑な小路。